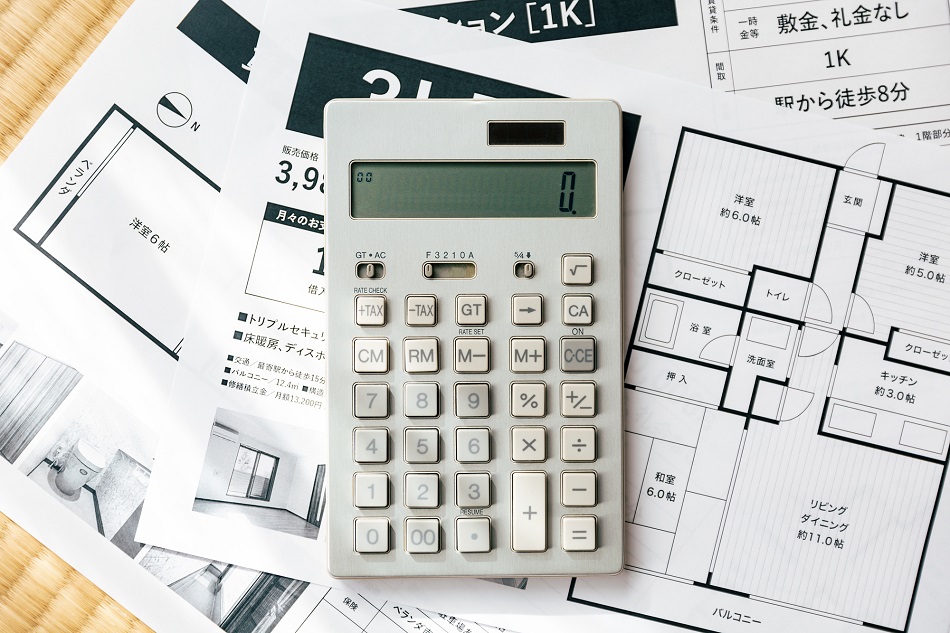確定申告とは、1月1日から12月31日までに発生した所得を税務署に申告し、税金を納める手続きのことです。
マンションを売却すると、場合によっては確定申告が必要となることがあります。
では確定申告は、どのようなときに必要で、どのようなときに不要なのでしょうか。この記事では「マンション売却の確定申告」について解説します。
不動産の売却のお問い合わせやご相談は「長谷工の仲介」へ
マンション売却で確定申告が必要となるのは?
給与所得者である会社員は、普段は確定申告をおこないません。しかしマンションを売却して「譲渡所得」が発生した場合、会社員であっても確定申告が必要となります。譲渡所得とは、簡単にいうと「売却益」のことを指します。
一方、譲渡損失(売却損)が発生した場合は確定申告は不要です。そのため「譲渡所得が発生すれば確定申告が必要」、「譲渡損失が発生すれば確定申告は不要」というのが原則的なルールとなります。
ただし例外があり、マンション売却時の税金控除や特例を利用する場合には確定申告が必要です。
税金の還付が受けられる特例は、譲渡損失が発生したときに利用できる制度になります。
よって、譲渡損失が発生しても、税金還付が受けられる特例を利用したい場合は確定申告が必要になります。
まとめると下表のようになります。
| 確定申告が必要なケース | 確定申告が不要なケース |
|---|---|
|
|
マンション売却で確定申告をしなかったらどうなる?
確定申告の必要がある人(譲渡所得がプラスの人)が確定申告をしなかった場合は税額に応じた税金が加算されることになります。
確定申告を忘れた場合は無申告加算税が課され、申告納税額が過少申告だった場合は過少申告加算税が課されます。また、意図的に事実を隠蔽すれば重加算税、申告しても期限までに完納しない場合には延滞税が課されます。
一方、確定申告が不要な人にも税務署から「お尋ね」と呼ばれるアンケート調査が来ることがあります。
お尋ねとは、税務署が「この人は本当に譲渡所得が出ていないのだろうか?」などの念のため確認するための調査になります。確定申告が不要な人は、売却価格等の事実を回答すれば問題ありません。
確定申告の手順や流れ
ここからは、確定申告の流れについて解説します。
まずは確定申告で必要となる書類を揃える
確定申告では必要となる書類を用意します。自分で揃える書類と税務署で入手する書類があるため、詳しく見ていきましょう。
自分で用意する書類
確定申告では、一般的に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 入手方法 |
|---|---|
| 売却したマンションの謄本 | 法務局(窓口申請:600円) |
| 住民票の除票(※1) | 市町村役場(300~400円)(※2) |
| 売却物件の購入時の売買契約書等 | 売主様が保有 |
| 売却物件の売却時の売買契約書等 | 売主様が保有 |
| 費用を証明する領収書等 | 売主様が保有 |
※1契約日前日までに住民票の住所と譲渡資産の所在地が異なる場合は必要になります。
※2各種手続きにかかる費用は市区町村によって異なる場合がございます。
なお、特例を利用する場合には、特例ごとに必要な書類が異なります。特例ごとの書類は、「マンション売却時の税金控除や特例とは?」をご参照ください。
税務署から入手する書類
税務署から入手する書類は「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」です。国税庁のホームページから無料でダウンロードすることが可能です。
譲渡所得税の計算をおこなう
譲渡所得の計算式は以下のようになります。ここからは譲渡所得の計算方法を具体的に解説します。
譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
譲渡価額・取得費・譲渡費用の算出
(1)譲渡価額
譲渡価額とは売却で得た収入のことを指します。具体的な額は以下の計算式で求められます。
譲渡価額 = 売却価格 + 固定資産税等清算金
マンションの売却では通常、買主様から固定資産税等清算金を受領することで固定資産税および都市計画税の実質的な負担を買主様側へ移転します。
ただし、1年の途中でマンションを売ったとしても、その年の固定資産税等の納税義務者は1月1日時点の所有者のままになります。納税義務者が変わるわけではないので、買主様から受け取った固定資産税等清算金は事実上の物件価格の一部という扱いになり、収入金額に加えられます。
なお、固定資産税等の清算金は起算日が1月1日の場合と4月1日の場合があります。契約時に確認するようにしましょう。
一方、マンションの売却では管理費および修繕積立金も清算するのが一般的です。管理費および修繕積立金は、引き渡し日以降は買主様の負担として日割り計算します。
買主様から受け取った「管理費および修繕積立金の清算金」は固定資産税等とは異なり、売主様による「立て替え金」という扱いになり、収入金額に加えなくてもよい扱いになります。
(2)取得費
取得費とは、土地は土地購入額、建物は建物購入額から減価償却費を控除したものとなります。減価償却費とは、会計上の建物価値が目減りした額を表したものです。
取得費の計算式は、以下のようになります。
取得費 = 土地購入価額 + (建物購入価額 - 減価償却費)
マイホームのマンションの場合、減価償却費は以下の式で計算します。
減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率は建物の構造によって決まっており、構造別のマイホームの償却率は以下のとおりです。
| 構造 | 非事業用(マイホーム等)の償却率 |
|---|---|
| 木造 | 0.031 |
| 木造モルタル | 0.034 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 0.036 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 0.025 |
| 鉄骨造(4mm超) | 0.020 |
| 鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
構造が「鉄筋コンクリート造」または「鉄骨鉄筋コンクリート造」の場合は、「0.015」を用います。
経過年数とは築年数ではなく、所有期間のことを指します。経過年数は1年単位であり、端数が6ヵ月以上の場合は1年切り上げ、6ヵ月未満の場合は切り捨てをして求めます。
例えば、所有期間が「2008年1月~2023年9月」であれば、15年8ヵ月なので切り上げとなり経過年数は16年となります。
(3)譲渡費用
譲渡費用とは売却に直接要した費用を指します。
ただし、売却に関連する支出が全て譲渡費用として認められるわけではなく、譲渡費用として計上できるものは限定的です。
譲渡費用になるものとならないものは以下のとおりです。
| 譲渡費用に認められるもの | 譲渡費用に認められないもの |
|---|---|
|
|
譲渡所得・譲渡所得の算出
それでは、具体的に譲渡所得を算出してみます。
(条件)
売却価格:5,500万円
固定資産税等清算金:6万円
譲渡費用:174万円(仲介手数料:171万円、印紙税:3万円)
構造:鉄筋コンクリート造
購入時の土地価格:3,000万円
購入時の建物価格:2,000万円
経過年数:15年
(計算)
最初に譲渡価額を計算します。
譲渡価額 = 売却価格 + 固定資産税等清算金
= 5,500万円 + 6万円
= 5,506万円
次に取得費を計算します。
減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
= 2,000万円× 0.9 × 0.015 × 15年
= 405万円
取得費 = 土地購入価額 + (建物購入価額 - 減価償却費)
= 3,000万円 + (2,000万円 - 405万円)
= 4,595万円
最後に譲渡所得を求めます。
譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
= 5,506万円 ― (4,595万円 + 174万円)
= 737万円
譲渡所得が発生しており、確定申告が必要です。
確定申告書を作成する
譲渡所得の計算方法がわかったら、確定申告書を作成します。
確定申告は、直前になると自治体が無料相談会を開催するケースが多く、税理士が無料で確定申告書の書き方を指南してくれます。はじめて確定申告をおこなう方はこうした無料相談会も上手に活用することをおすすめします。
確定申告の作成方法についてはこちらの記事をご覧ください。
マンション売却の確定申告書の書き方は?手続きの流れも併せて解説
税務署に確定申告書を提出する
確定申告の期間は、一般的に売却した翌年の2月16日から3月15日までです。土日の関係で日にちが若干ずれる年もあるため確認しておきましょう。
インターネット申請、最寄りの税務署に直接持参、または郵送のいずれかで提出可能です。
マンション売却時の税金控除や特例とは?
マイホームのマンションを売却したときに利用できる主な特例は以下の5つです。
| 利用場面 | 特例名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 譲渡益が生じたときの節税特例 | 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から3,000万円を控除できる。 |
| 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 所有期間が10年超のマイホームを売ると税率が下がる。 | |
| 譲渡損失が生じたときの税金還付を受けられる特例 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 | 売却物件で発生した譲渡損失を他の所得と損益通算ができる(買い替えを要件とする)。 |
| 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 | 売却物件で返済しきれなかったローン残債の額を損失として他の所得と損益通算ができる(買い替えは要件としない)。 |
それぞれの特例で必要となる書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 3,000万円の特別控除 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 特定の居住用財産の買換え特例 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 | 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除票住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 売却物件の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 購入物件の登記事項証明書 | ― | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 新しい住民票 | ― | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 住宅借入金の残高証明書 | ― | ― | ― | 〇(購入物件) | 〇(売却物件) |
なお、「譲渡益が生じたときの節税特例」は、3つとも「購入物件の住宅ローン控除」と併用できない特例です。
「購入物件の住宅ローン控除」と「譲渡益が生じたときの節税特例」は選択適用となっており、節税効果の高いほうを選択することがポイントとなります。
具体的なマンション売却にかかる税金や特例についてはこちらの記事で紹介していますのでご覧ください。
マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や知っておきたい控除について徹底解説
確定申告で悩んだらプロにご相談を
マンション売却の税金の知識は専門的で複雑なので、調べてもわからなかったり間違ってしまうことがあります。
そのため、早い段階からプロに相談することをおすすめします。プロに相談すれば自分で情報を取捨選択する手間が省け、正確に手続きを進められるようになります。
長谷工の仲介では税務相談サービスをご用意していますので、ぜひご利用ください。
まとめ
ここまで、マンション売却の確定申告について解説してきました。
マンション売却では、「譲渡益が生じている場合」または「特例を利用する場合」は確定申告をする必要があります。一方「譲渡損失が生じており、かつ特例も利用しない場合」は確定申告は不要です。
長谷工の仲介の税務相談サービスも上手に活用しながら、手続きを進めていくようにしましょう。
※本記事の内容は2022年7月12日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。